大阪歴史博物館 ― 2025年05月23日
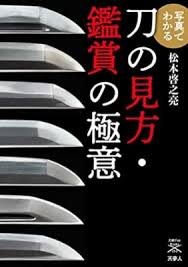
大阪歴史博物館を訪れた。特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」が開催されていた。日本刀の美しい姿が完成したのは平安時代とされ、先の大戦後の一時期を除き、約1000年にわたり製作が続けられてきた。その背景には、時代ごとに活躍する刀匠の存在がある。現在の国宝や重要文化財も、当初は新作刀だったように、現代の新作刀から未来の国宝が生まれる可能性がある。本展は、国内最大の刀匠団体「全日本刀匠会」設立50周年を記念し、1000年にわたる日本刀の歴史とその継承の姿を紹介している。外国人を含め多くの来館者が見学していたが、その価値がいまいち理解できなかった。確かに、1000年の歴史を持つ日本刀の制作技術が現代まで受け継がれていることは価値がある。しかし、ケースに飾られた日本刀の前でじっくりと刀を眺める来館者と自分とは異なる価値観があることは分かるが、どれも同じように見える刀の陳列を前に、唸るほどの感銘を受ける感覚がわからなかったのが残念だ。
常設展の難波京の説明のほうが、自分には興味深かった。難波京(なにわきょう)は、古代日本における都城の一つである。飛鳥時代の孝徳天皇が645年の大化の改新後に遷都し、難波長柄豊埼宮(なにわのながらのとよさきのみや)を造営したことが始まりとされる。その後、奈良時代の聖武天皇が744年に再び難波京へ遷都し、後期難波宮が建設された。難波京は瀬戸内海の東端に位置し、外交や物流の拠点として重要な役割を果たした。遣唐使の出発地としても知られ、海上交通の要衝であった。奈良時代には条坊制が導入され、都市計画が整備されたことが発掘調査によって確認されている。しかし、聖武天皇は翌年には平城京へ戻り、難波京は副都として存続した。8世紀末には摂津職が廃止され、難波京は都城としての役割を終えた。現在、大阪市中央区の法円坂周辺で難波宮跡が発掘されており、古代都市の姿が徐々に明らかになっている。難波京は上町台地の北端に位置し、淀川や大和川の流れ込む河内湖の沿岸に広がる一角にあった。近隣には難波津という港が存在し、外交や物流の拠点として重要な役割を果たしたという。大阪北部が「湖」だったというのは初めて知った。
この経緯をボランティアの方が端的に説明していたのが面白かった。権力者・蘇我入鹿を暗殺した中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)は、天皇中心の政治体制を構築するため、飛鳥の田舎を離れ、大阪に国際都市を作ろうとした。しかし、孝徳天皇と仲違いした中大兄皇子も奈良へ戻っており、天皇の崩御を契機にオピニオンリーダーを失った人々も奈良へ戻った。その90年後、聖武天皇の時代には権力闘争が激化し、首都・奈良だけでなく副都心の必要性が高まり、恭仁京や紫香楽宮への遷都を繰り返した。そして、貿易の拠点として再び難波京が重要視され、第二次難波京が成立した。しかし、財政的に維持できず、奈良へ戻ることになった。その後も仏教勢力との対立が続き、桓武天皇が長岡京へ遷都する際に難波京を解体し、その資材をリユースしたという。この解説は非常に分かりやすく、感心した。1日2回ほど説明を行っているとのことだが、自分の好きなことを語りながら老後を過ごすというのは、とても楽しそうでうらやましく思った。
常設展の難波京の説明のほうが、自分には興味深かった。難波京(なにわきょう)は、古代日本における都城の一つである。飛鳥時代の孝徳天皇が645年の大化の改新後に遷都し、難波長柄豊埼宮(なにわのながらのとよさきのみや)を造営したことが始まりとされる。その後、奈良時代の聖武天皇が744年に再び難波京へ遷都し、後期難波宮が建設された。難波京は瀬戸内海の東端に位置し、外交や物流の拠点として重要な役割を果たした。遣唐使の出発地としても知られ、海上交通の要衝であった。奈良時代には条坊制が導入され、都市計画が整備されたことが発掘調査によって確認されている。しかし、聖武天皇は翌年には平城京へ戻り、難波京は副都として存続した。8世紀末には摂津職が廃止され、難波京は都城としての役割を終えた。現在、大阪市中央区の法円坂周辺で難波宮跡が発掘されており、古代都市の姿が徐々に明らかになっている。難波京は上町台地の北端に位置し、淀川や大和川の流れ込む河内湖の沿岸に広がる一角にあった。近隣には難波津という港が存在し、外交や物流の拠点として重要な役割を果たしたという。大阪北部が「湖」だったというのは初めて知った。
この経緯をボランティアの方が端的に説明していたのが面白かった。権力者・蘇我入鹿を暗殺した中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)は、天皇中心の政治体制を構築するため、飛鳥の田舎を離れ、大阪に国際都市を作ろうとした。しかし、孝徳天皇と仲違いした中大兄皇子も奈良へ戻っており、天皇の崩御を契機にオピニオンリーダーを失った人々も奈良へ戻った。その90年後、聖武天皇の時代には権力闘争が激化し、首都・奈良だけでなく副都心の必要性が高まり、恭仁京や紫香楽宮への遷都を繰り返した。そして、貿易の拠点として再び難波京が重要視され、第二次難波京が成立した。しかし、財政的に維持できず、奈良へ戻ることになった。その後も仏教勢力との対立が続き、桓武天皇が長岡京へ遷都する際に難波京を解体し、その資材をリユースしたという。この解説は非常に分かりやすく、感心した。1日2回ほど説明を行っているとのことだが、自分の好きなことを語りながら老後を過ごすというのは、とても楽しそうでうらやましく思った。